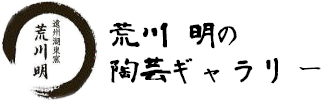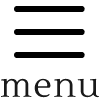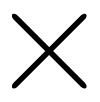代表者挨拶

ご挨拶
荒川明の陶芸ギャラリーの荒川明です。
浜松市の北に位置する
静岡県浜松市北区引佐町奥山に工房があります。
当工房は城ヶ峰のハイキングコースの麓にあり
当工房より先は民家がありません。
車は1日1台、森林組合の車が通るかどうか位です。
自然は昭和の30年代がそのまま残っています。
今でも天然の蛍が見られ、夜は星が満天に輝いております。
そんな自然豊かな環境の中陶芸作品を造っております。
こどものころは
子供の頃は体が弱く、小学校の図書館の本を全部読みつくし借りる本がない位読みました。
又美術の先生から切り絵を教えて頂きました。
建築設計の世界へ。
建築を勉強しながら20歳位から陶芸に興味を
持ち、独学、建築設計事務所を経営しながら
29歳に開窯
当初は趣味で陶芸作品を造っており
陶芸家になるなんて、夢にも思っていませんでした。
地元の市展に出品し 入賞
富岳展公募展 入選
全国公募展で出品し、自分の実力を試したいと思い
創造美述会に出展し大きな成果を頂きました。
作陶10周年の時 東急百貨店 本店にて個展
その時は設計事務所を経営しながら個展開催
建築設計と陶芸の2足のわらじをはきながら
1999年 創造展にて文部大臣奨励賞受賞
2000年 NHKBSやきもの探訪
2001年~ 『私の陶芸』ブテック社
NO1~8監修 寸評及びコンテスト審査委員
2002年 静岡県浜松市北区引佐町奥山の大自然の中に
工房である奥山芸術の里・荒川明陶房開設
そんな時『私の陶芸』ブテック社の編集長さん
から大自然の中で陶芸家を育てたらどんな
陶芸家になるんだろうね!と言われて
陶芸作家養成所を開設
昼間 設計事務所の仕事をする時間がなくなり
陶芸研修所 釉薬研究 陶芸作品の制作活動を
始めました。
2003年 自分で考案した薪窯を制作
現在ではあまり焼成されていない、
志野 鳴海織部 御本手 天目を焼成
本格陶芸作品を!
日本の陶芸作品のを良さを知ってもらいたい!
そんな思いで
2009年 楽天市場にてネット販売販売を開始
ネットに載せればすぐ売れると思っていました。
陶芸作品は手に持って質感を感じ感触を楽しむのが
作品を選ぶコツだからネットで売れない。のささやきが聞こえて来ました。
全く作品が売れず
ではどうしたら陶芸の良さをネットで伝えたらいいのか?
作品の写真を正面、正面反対、中、表面を拡大した部分、高台(底)
と作品のチェックポイントを写真にて画像をアップしました。
大きさの判断は抹茶茶碗は茶筅(お茶をたてる道具)を横においた画像
ぐいのみ、湯のみ等は荒川が手に持って写真を写しました。
まだまだ伝えきれませんが気がついたところから直して行きたいと思っております
お茶を飲むのに100均のお湯のみでも飲めます。
荒川 明の湯のみで飲むのと100均の湯のみの違いはなんですか?
★湯のみは毎日使うもので、まずは使いやすい
★土もの湯のみですから熱いお茶を入れても土の厚みをとうして熱くならない!
世界に1つの作品
そんな思いでこれからも釉薬の実験しながら
作品を見れば荒川明の作品だとわかってもらえる
作品造りをしてい所在です。
陶芸作家 荒川明は土にこだわり、釉にこだわり、焼成にこだわり、陶芸製作を日々行っております。
1. 土のこだわり
作品により萩土、備前土、信楽土、美濃土を仕入、自分に合った土にする為ブレンドします。



志野茶碗、鳴海織部茶碗の為には山から掘った原土を上写真の様に石臼と杵でつき土作りを致します。土練きでブレンド中
2. 作品造りのこだわり
1つ1つ手作り、同じ形は造らず、形を変え文様を変えて1品限定作品を造ります。




3. 釉薬のこだわり
釉薬(色をつける薬)も自分で工夫して独自の釉薬を作ります。




4. 焼成(焼き方)のこだわり
荒川明は焼締、灰被り、志野、鳴海織部、御本手、天目等を薪窯で3昼夜焼成致します。
種々の釉薬物を薪窯で焼成するのは非常に大変ですで技術が必要です。薪窯の特性で
製品にならない作品も多く、その中で特に良い焼き上がり作品を選抜しております。

焼締作品の藁を丁寧に巻くと美しい火襷が出ます

薪窯の窯詰めは作品が棚板にくっつかなくするため耐火土をつけます。

3日間の焼成!正面2ケ所、左右2ヶ所に薪を入れる

志野、鳴海織部、焼締作品窯開け風景